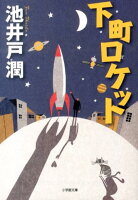「坂の上の雲5 / 司馬遼太郎」の感想・あらすじ
2025/08/20
点数
72点
感想
以下が主な内容だった。
- バルチック艦隊のロジェストウェンスキーは官僚的な性格であり、艦隊を率いるには向いていなかった。
- 明石元二郎はヨーロッパで諜報活動を行い、ロシアの帝政が崩壊するように尽力した。
- 乃木軍が旅順から合流した日本軍は奉天攻めを開始し、戦力はロシア軍が上回っていたがクロパトキンの判断ミスなどによりロシア軍は退却した。
明石元二郎の諜報活動についての話は、退屈で面白くなかった。
ロジェストウェンスキーとクロパトキンは戦争には不向きな人物であり、それがロシアにとっては不運だったという印象が残った。
あらすじ
黄色い煙突
- 黒い艦体と黄色い煙突をもったバルチック艦隊は1月9日にノシベに到着してから、2ヶ月間も足踏みすることになった。
- 碇泊中、技師ポリトゥスキーは艦艇の修理で忙しかった。
- 艦底に海藻や貝殻が付着して速力が出ないため、ドックがない状況で潜水夫が掃除を行ったが、それは気休めにすぎなかった。
- ロシアは皇帝による専制政治であり批判機関を持たないため、正しい決定や計画を立てることができなかった。それが負けた最大の理由である。
大諜報
- 明石元二郎は児玉の秘密命令により、2年間ヨーロッパでロシア革命を扇動した。
- ポーランド、フィンランドはロシアのに武力で独立を阻止されていた。
スウェーデンもロシアに怯えていた。
彼らは日本に同情的であり、ロシア国内の革命団体と手を結んでいる政党もあった。 - ペテルブルグの日本公使館にいた明石らは、開戦後の明治37年2月にストックホルムに移った。
列車が駅に着くと、歓迎する人たちが待っていた。 - 日本と戦っているロシア軍には多くのポーランド人が含まれていた。
彼らは憎むべきロシアのために、同志であるはずの日本と戦わされていた。 - 明石は亡命フィンランド人の独立運動家であるシリヤスクとカストレンと接触、工作者や諜報者に資金を渡したり、パリで不平党の首領を集めて5日間に及ぶ大集会を開くなどした。
- パリ会議以来情勢は一変し、ポーランドやロシアで激烈な革命運動が頻発した。
- 明治38年1月、革命的な性格をもたない宗教儀礼的な請願デモに対して政府が武力弾圧した「血の日曜日事件」が起きた。
ロシア政府が革命に過剰に反応していたために起きたこの事件は革命機運を躍進させ、大衆は「もはや皇帝は自分たちの味方ではない」ことを知った。
乃木軍の北進
- 明治38年1月11日、津野田参謀は乃木に命じられ、ステッセルらが旅順から大連までの馬車や列車で移動するのを見送った。
- 乃木軍は総司令部から「2月中旬までに遼陽付近に集結」という命令を受け、1月24日に柳樹房を出発し北進を開始した。
- 伊地知参謀長は旅順要塞司令官という閑職に回された。
新たに乃木軍の参謀長となった小泉正保は、汽車が鉄橋の上に止まっていることに気付かず用便のために飛び降り橋の下に落下、重傷を負った。
水の枯れた川底で発見された小泉は、遼陽停車場で野戦病院に運び込まれた。
その後、小泉は本国へ移送され、代わりに松永正敏が2月1日に赴任したが、松永は黄疸に罹っており、参謀副長の河合操が代行することになった。 - 乃木軍は遼陽に着くと、本国からの兵力の補充を待った。
鎮海湾
- 東郷が座乗する三笠は明治38年2月14日に呉港を出発し佐世保港に入り、20日に佐世保を出た。
このとき軍艦行進曲が艦上で演奏された。 - 東郷艦隊はバルチック艦隊が来るまでの隠れ場所として選んだ鎮海湾で錨を下ろし、5月までの3ヶ月間射撃訓練を徹底的に行なった。
印度洋
- ロジェストウェンスキーは日本と海戦をするつもりはなく、いかに損害少なくウラジオストックに辿り着くことができるかを考えていた。
- ロジェストウェンスキーは皇帝のような独裁で全艦隊を統御し、部下の全艦長が無能だと思い込んでいた。
- 3月15日、「明日正午までに蒸気力を準備せよ」との命令があり石炭や食料の積み込みが行われ、16日に大艦隊は出発し印度洋を東進した。
奉天
- クロパトキンが奉天に32万の大軍を動員したのに対し、日本の兵力は25万であった。
これだけの兵力が対決するのは、世界戦史上初であった。 - 財政が逼迫していたため、東京の政府と大本営は戦争の早期終結を望んでいた。
また、春になればロシア軍に新たな援軍が到着し、河川も解氷して軍の機動が制限されるため、日本軍は冬のうちに決着をつける必要があった。 - 児玉は2月25日を作戦発動の日とした。
松川敏胤が立案した作戦は「まず敵の左を突き、次に右を突く。そして左右に兵力が集中したところで中央を突破する」という奇策であった。 - 日本軍最右翼に置かれて敵の左を突くのは鴨緑江軍、最左翼に置かれて敵の右翼を突くのは乃木軍、中央突破は奥軍と野津軍の役目となった。
- 鴨緑江軍は「ウラジオストックや樺太を占領し、講和談判でそこをもらう」という、長岡外史が立案した戦略用の一軍である。
不足している兵力から引き抜いて新設した一軍であり、児玉や松川は創設に大反対であった。
会戦
- クロパトキンはもう一度黒溝台を攻めるように命じた。
グリッペンベルグがそれをやった時は非協力的であったが、それは「成功したら功はグリッペンベルグにゆき、自分は失落する」という理由であった。
もしそれが実行されたら好古の軍は全滅したはずだが、クロパトキンは乃木軍の行方を気にしたため実行しなかった。 - クロパトキンには「乃木軍は日本軍の右翼に出てロシア軍の背後を狙ってくる」という誤報が届いていた。
実際には乃木軍は左翼へ展開していた。
クロパトキンは「乃木軍がどこから出てくるかわからない」「日本軍が我が軍の後方鉄道を奇襲しようとしている」という恐怖から黒溝台攻めを中止したかったが、軍司令官の反対があり2月25日に攻勢開始することになった。 - クロパトキンが西部戦線に一大攻勢をかけようとしたところ、東部戦線に日本の鴨緑江軍が出現した。
彼はそれを乃木軍と勘違いしたため作戦を変更し、全兵力の20%を東部戦線に移動させてしまった。 - その後に乃木軍が西部戦線に出現すると、クロパトキンは兵力を再び移動させるという右往左往を演じた。
- 大山と児玉は「この会戦に勝ったとしても戦力は尽きてしまう」と覚悟していたため、優勢勝ちの状態にして講和に持っていきたいと考えていた。
- 東部戦線の鴨緑江軍は2月23日に行軍を開始した。
西部戦線の乃木軍は27日に行軍を開始、課せられた作戦は「迂回して敵の背後をつく」というものであったが、乃木はそれを「全軍の犠牲になる」と受け取った。 - 乃木軍はロシア軍の激しい攻撃を受けたが、なんとか奉天の北方に出ることができた。
中央の奥軍は3月2日に敵を撃破した。 - 好古は乃木軍の北進を円滑にし、奉天北方の鉄道を破壊するように命じられた。
3日には大房身という村落でロシアの支隊と激突、好古隊は騎兵を馬からおろして防御陣地に入れ、4時間に及ぶ猛烈な火力戦の末に敵を追い払った。
4日、好古は乃木軍の先頭にあって奉天西方に出た。 - 3月5日6日の2日間、ロシア軍は大兵力で乃木軍を攻撃した。
野津軍も苦戦していた。
しかし、7日になるとなぜかロシア軍はクロパトキンの命令により退却した。 - 日本軍の作戦は「小部隊が大部隊を包囲する」という非常識なものであったが、大山と児玉は「クロパトキンなら幻惑されて守りに入るはず」という賭けに出たのである。